はじめに
脳卒中後のリハビリで、左側にあるはずの世界が“なかったこと”になる――そんな不可解な現象に直面したことはありませんか?
半側空間無視(Unilateral Spatial Neglect:USN)は、視力そのものの問題ではなく、注意の方位がゆがむことで起こる症候です。患者さんは“見えない”のではなく、気づかない/探しに行かない。だからこそ、眼鏡や視野検査だけでは掴みきれず、評価の仕方と関わり方がアウトカムを左右します。
本稿では、臨床で役立つ自己中心座標 vs 物体中心座標の見分け方から、視覚探索訓練やプリズム順応などの介入の組み立て方、さらに話題の**「燃える家(無意識処理)」と表象無視(頭の中の地図でも左が抜ける)まで、リハ職・看護・学生が明日から実践できる実務視点で一気に整理します。
3つの約束
- 専門用語は噛み砕いて提示
- やる順番が分かる構成
- 研究の面白さ(燃える家/表象無視)は臨床の意思決定に繋げる
半側空間無視(USN)徹底ガイド:臨床から表象まで
1. USNの本質:視力ではなく「注意の偏り」
- 定義:脳損傷(多くは右半球)後、反対側(典型は左)の空間や物体へ自発的に注意を向けられない状態。
- キーワード:見えているのに気づかない/探索しない、両側同時提示で左が消える(消去)。
よくある誤解
- ×「視野が欠けているから」→ 同名半盲は視野欠損。視線を動かせば拾えることが多い。
- 〇「注意が右へ引っ張られている」→ 探索開始点が右、頭部・眼球の回旋も右偏位しやすい。
2. 自己中心座標 vs 物体中心座標(臨床のキモ)
2-1 定義
- 自己中心(Egocentric):自分(眼・頭・体)を原点に、**“自分の左”**が落ちる。
- 物体中心(Allocentric):各**物体そのものの“左半分”**が落ちる。
2-2 見分けの実戦フロー
- 抹消課題(A4中央に星・丸・四角を散布)
- 左ゾーン全体のヒットが少ない → 自己中心寄り
- ページ全域で各ターゲットの左半分を落とす → 物体中心寄り
- 線分二等分
- 一貫して右寄り → 自己中心優位
- 小図形でも左側を短く処理 → 物体中心関与
- 模写・描画
- 図全体の左がスカスカ → 自己中心
- 花びら/星の左枝だけ欠ける → 物体中心
- 読み
- 行頭(紙の左側)を取り逃す → 自己中心
- 単語の左半分の字を飛ばす → 物体中心
2-3 ADLでの顔つき
- 自己中心:皿の左側を残す/左袖を通さない/車椅子で左に接触。
- 物体中心:ボタンの左半分の位置合わせを誤る/ラベルの左側情報を読み漏らす。
3. 代表的評価と読み方(紙筆+機能)
- 紙筆:抹消課題、線分二等分、模写・描画(必要に応じてBIT)。
- 機能:**Catherine Bergego Scale(CBS)**で更衣・食事・移動など日常の左無視を0–30点で定量化。
- 観察:視線・頭部偏位、左側物品の取りこぼし、病態失認の有無。
読み方のコツ
- 自己中心:用紙全体の左が抜ける傾向
- 物体中心:各アイテムの左半分が系統的に抜ける
4. 介入の優先順位と設計(“やる順番”が命)
4-1 基本戦略(コア)
- 視覚探索訓練(第一選択)
- 左端アンカー(太線・テープ・付箋)を設定
- 左端まで頭部・眼球を大きく振る→行頭復帰を声かけ
- 反復でアンカーを段階的に薄める/外す(一般化)
- プリズム順応
- 右方10–12°シフトのプリズム装用下で左への到達課題を反復
- 脱着後の左方向再較正の残存を活かし、探索課題へブリッジ
- リムブアクティベーション
- 左上肢の随意運動・自発使用を増やし、左空間の体性感覚入力を強化
4-2 補助戦略(症例に合わせて)
- 感覚刺激:頸筋振動、オプトキネティック刺激、温冷刺激(短期効果)。
- 脳刺激:rTMS/tDCS(施設・研究ベース)。
- 薬物補助:NA/DA作動薬(適応を慎重に)。
- VR/AR・フィードバック:視覚×体性感覚のマルチモーダルで探索を誘導。
4-3 作業療法・看護の具体策
- 環境調整:重要物は計画的に左へ、呼びかけも左から。
- 動作手順:更衣は左から開始、配膳は左起点、移動ルートは左能動使用を促す設計。
- 身体志向:左手にリストバンド/軽い振動、鏡療法、ボディスキーマ再学習。
- 安全:左側の障害物にテープ/コーンで可視化。
5. 情動処理と「燃える家」:無意識はどこまで助けるか
- 古典的観察:同じ家の絵2枚(片方は左側が火事)。患者は「違いがわからない」と言いながら、**“住むなら燃えてない家”**を選びがち。
- 含意:顕在報告が欠けても、無意識レベルの処理が行動選好に影響する可能性。
- ただし:個人差が大きく、再現性には限界。**「必ず起こる」**とは言えない。
- 臨床Tips:言語報告(見える/見えない)と選好・反応を分けて評価。左側に高喚起の手がかり(注意アイコン、短い音/触覚)を補助的に使い、探索のスイッチに。基本は探索訓練。
6. 表象無視(representational / imaginal neglect)
6-1 何が起きている?
- USNは現実空間だけでなく、頭の中のイメージ空間でも“左”が抜けることがある。
- 視点を反転させると、**心的イメージ上の“左”**が常に抜ける――自己中心の表象無視の所見。
6-2 臨床での評価アイデア
- 病棟マップの想起:ナースステーションに“立っている”想像で、見えるものを時計回りに列挙。出発点を変えて視点反転も。
- 自宅間取り/近所地図:同様に視点を切り替え、言い落とし側の一貫性を見る。
- 想像描画(時計・顔・花):目を閉じて部位名を挙げる課題。
- 数直線(二等分):例「2と6の真ん中は?」――右寄りの答えになりがちかを確認(反応時間も記録)。
6-3 介入の工夫(表象×現実をつなぐ)
- 心的探索訓練:イメージ上でも左端アンカー語(例「北→西→南→東」)を用い、実課題と整合。
- 視点反転リハ:想像の出発点を変え、左右双方を言語でスキャンする癖付け。
- マルチモーダル同期:イメージで想起しづらい左要素に、実課題の音/触覚合図を同期させて“左ジャンプ”を学習。
- 系列の空間化:手順・曜日・数列を左→右の心的地図として扱い、左起点の取りこぼしを是正。
7. 予後に響くポイント
- 初期重症、病態失認の合併、広範な右半球損傷、高齢、注意/覚醒低下があると回復は遅れやすい。
- 重要なのは早期からの系統的介入と、心的探索(表象)まで広げた訓練の併用。
8. まとめ(臨床判断の指針)
- USNのコアは注意の偏り。自己中心と物体中心を見分ける。
- 介入の軸は視覚探索訓練。プリズム、リム活性化、補助刺激を段階的に。
- 「燃える家」は無意識処理の可能性を示唆するが一般化は禁物。評価は言語報告と選好を分けて。
- 表象無視は心の中の空間でも“左”が抜け得る。想起+視点反転+数直線で拾い、表象×現実をつなげて訓練。

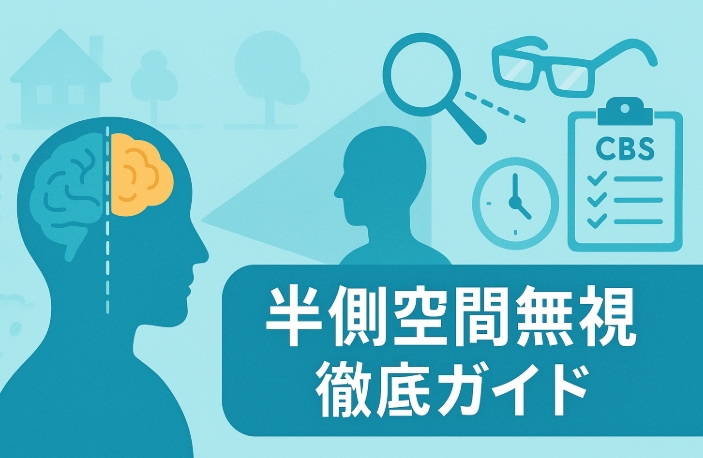


コメント