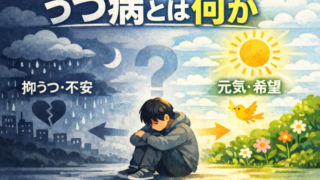 Uncategorized
Uncategorized うつ病とは何か
――感情はなぜ私たちを守り、そして時に私たちの生活を崩してしまうのか―― 「うつ病」と聞いたとき、多くの人は“気分が落ち込む病気”“やる気が出なくなる状態”といったイメージを思い浮かべるかもしれませんが、実際のうつ病は単なる気分の落ち込みと...
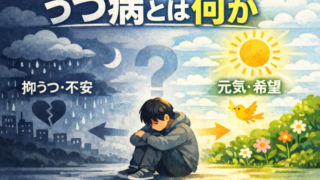 Uncategorized
Uncategorized  Uncategorized
Uncategorized  Uncategorized
Uncategorized  Uncategorized
Uncategorized 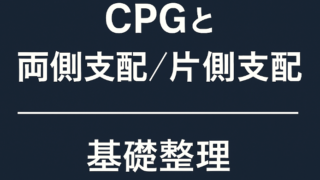 Uncategorized
Uncategorized  Uncategorized
Uncategorized 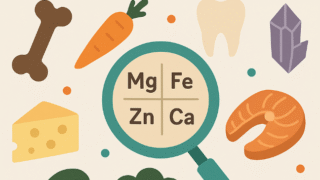 Uncategorized
Uncategorized 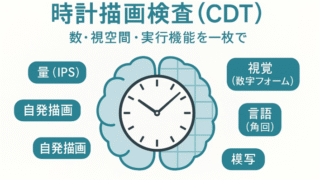 Uncategorized
Uncategorized 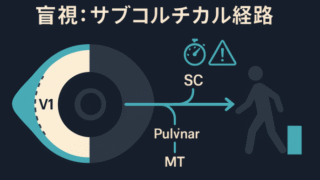 Uncategorized
Uncategorized 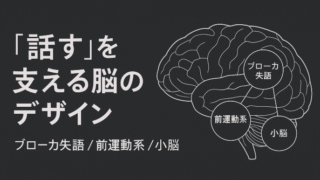 Uncategorized
Uncategorized