ある朝、いつものスニーカーを履こうとして気づく。靴ひもを結ぶ指が、なんだかスロー再生。歩き出すと片腕の振りが省エネモード。鏡の中の表情はミニマリスト。
それがパーキンソン病(PD)の“入り口”かもしれません。
一言で言うと?
脳の黒質で作られるドーパミンが足りなくなる進行性の病気。
ドーパミンは「動きにGOサインを出す体のリモコン」。信号が弱くなると、動き出しにくい・小さくなる・震える・バランスを崩しやすいが現れます。しかも便秘や睡眠の乱れ、嗅覚低下、気分の落ち込みなど**“運動以外”のサイン**も多いのが特徴です。
物語の“プロローグ”:前駆期という長い序章
- 嗅覚低下・便秘・レム睡眠行動障害(RBD)・起立性低血圧などが、運動症状の5〜20年前から静かに始まることがあります。
- 病理の主役はαシヌクレインの異常凝集(=レビー小体の足跡)。広がりは嗅球や腸管 → 脳幹 → 大脳皮質という“旅ルート”(Braak仮説)が有名。
セルフチェック(家族と一緒に)
香りが弱く感じる/若い頃から頑固な便秘/寝言や手足を振る夢の演技/立ち上がりで視界が暗い——がいくつか重なって続くなら、神経内科で相談を。
症状の“キャスト紹介”——運動と非運動、両方が主役
運動症状(コア)
- 無動・寡動:動きが遅い・小さい。歩幅が詰まる、字がだんだん小さくなる(微小字)。
- 筋強剛:こわばり。肩こり・背部痛の黒幕。
- 安静時振戦:じっとしているほど震えやすい“ピルローリング”。
- 姿勢反射障害:後方に引かれると踏ん張れない、方向転換でフラつく。
- フリージング(FOG):ドア前や狭所で足が床に貼りつく感覚。
非運動症状(クセ者だが生活を大きく左右)
- 自律神経:便秘、頻尿・尿意切迫、発汗異常、起立性低血圧。
- 睡眠:RBD、日中の眠気、分断睡眠。
- 感覚・痛み:肩背部痛、筋のこわばり痛、灼熱感。
- 嗅覚低下:食の楽しみが目減り。
- 気分・認知:不安・抑うつ・無関心、実行機能の低下(段取り・切替)。
- 嚥下・発声:声が小さく単調、むせやすい、体重減少。
豆知識:診察室で震えが弱く見えるのは“緊張や注意集中で安静時振戦が抑えられる”ことがあるから。家で撮った短い動画が診断の助けになります。
なぜ起きるの?——病理の裏側をちらり
- αシヌクレインが誤って折りたたまれ、小さな塊(オリゴマー)を作り、シナプスやミトコンドリアを傷めます。
- 黒質のドーパミン神経は代謝負荷が高く、酸化ストレスを受けやすい“脆弱なスペシャリスト”。だから選択的にダメージが出やすいのです。
診断と評価:探偵の三種の神器
- 臨床所見:片側優位の寡動+振戦/筋強剛、レボドパ反応性。
- 画像・検査(補助):MRI(除外目的)、DaT-SPECT(線条体ドパミン取り込み)、心筋MIBGシンチ(自律神経のダメージ)、PSG(RBD確定)。
- スケール:MDS-UPDRS、Hoehn & Yahr、QOLのPDQ-39、歩行のTUGや6MWTなど。
どこまで進んだ?——“物差し”と“実生活”
**Hoehn & Yahr(HY)**で1→5段階。
- 1:片側のみ。
- 2:両側だがバランス保たれる。
- 3:姿勢不安定が目立つ。
- 4–5:介助が必要/車いす中心。
大事なのはステージ番号より、今日の暮らしがどう変わったか。同じHYでも、リハ・住環境・服薬調整で体感は大きく違います。
治療:薬×デバイス×リハ=三位一体
① 薬——“演出の配役”
- L-ドーパ(+末梢阻害薬):主役。最も効く。
- ドーパミンアゴニスト:若年や初期で。副作用の眠気・衝動制御障害に注意。
- MAO-B/COMT阻害薬:効きの延長に。
- アマンタジン:ジスキネジア対策に有用。
- 抗コリン薬:振戦に効くが高齢では原則避ける。
進行でよくある相談
- ウェアリングオフ(切れ目で落ちる)→投与間隔や徐放製剤、併用薬で波をならす。
- ジスキネジア→L-ドーパ総量調整+アマンタジン。
② デバイス・外科——“システムの再配線”
- DBS(STN/GPi):運動合併症・振戦に強い味方(認知低下が強い場合は慎重)。
- 集束超音波(MRgFUS):難治性振戦の片側治療。
- 持続投与:腸管ジェル/皮下ポンプでオン・オフの波を小さく。
③ リハビリ——“最強の生活薬”
- 大きく・速く・リズムよく:LSVT BIG、トレッドミル、有酸素(目安150分/週を安全範囲で)。
- バランス・方向転換・デュアルタスク:小分けに毎日。
- FOG対策:床テープ・メトロノーム・掛け声の外部キュー。
- 言語・嚥下:LSVT LOUD、むせ予防の姿勢・一口量、“オフ”を避けた食事時間。
- 作業療法:ADLの分解、タイムテーブル化(オンに合わせて外出や家事)、道具工夫(滑り止め、取っ手、ボタンエイド等)。
生活をラクにする“トリック集”
- 服薬タイムは一定に:オン・オフのミニ日誌で診察が神速。
- タンパク質の“時間差攻撃”:L-ドーパと高タンパク食は少しずらすと吸収が安定する人も。
- 起立性低血圧:ゆっくり起立、弾性ストッキング、こまめな水分・塩分(持病に応じ医師と)。
- 家の“滑る・暗い・狭い”を減らす:段差解消、夜間照明、マットの滑り止め。
- 運動は“気合い”より“習慣”:3〜10分のミニセッション×複数回。
- 睡眠ハック:夕方以降のカフェイン控えめ、昼寝は20–30分、就床前のスマホは短め、RBDは寝具安全確保。
小さな症例スケッチ(現実との橋渡し)
ケースA:60代・初期。
“朝だけカチカチで、出かける頃には調子がいい”→起床前30分の内服+朝ストレッチで立ち上がりがスムーズに。通勤は早足ウォーク+一定の歩幅キューで転倒ゼロに。
ケースB:70代・中期。
「夕方の台所でつまずく」→LED照明の増設、回転時の“3歩法”、滑り止めマットで事故激減。買い物は“オン時間”にまとめる計画術で負担が半分に。
ケースC:70代・進行+FOG。
狭所で固まる→床テープとメトロノーム 100–110bpm。固まったら①止まる②姿勢を前に③一歩目“かかとトントン”。家族の合図キューが有効。
よくある誤解をサクッと訂正
- 「震えがない=PDじゃない」 → 震え目立たない型、あります。
- 「薬を早く使うと効かなくなる」 → 使い方次第。QOLのリターンが大きいことが多い。
- 「運動しても進行は止められないから無駄」 → 無駄じゃない。症状軽減・転倒予防・認知や気分にも好影響。
- 「診断がつくまで何もしない」 → 生活調整と運動は今からできる“副作用ゼロの治療”。
ここが危険サイン(受診の合図)
- 高熱+強いこわばり+意識混濁(悪性症候群の可能性)
- 突然の歩行不能/極端なすくみ(アキネティック・クライシス)
- 反復転倒、むせ・肺炎兆候、体重急減、強い幻視・せん妄
受診を最大化する“メモ術”
- オン・オフの時刻と症状(簡単でOK)
- 転倒・フリージングの場面(ドア前?方向転換?二重課題?)
- 睡眠・便秘・立ちくらみの頻度
- 飲んでいる薬の一覧(処方・市販・サプリ)
- 可能なら30秒のスマホ動画(歩行、立ち座り、すくみ)
家族・介護者に伝えたいコツ
- “急かさない”が最大の支援:スピードより段取りを。
- 転倒予防は“照明・動線・声かけ”:暗所と狭所、方向転換に声かけキュー。
- お金・ネット買い物の見守り:アゴニスト使用時は衝動制御障害の早期発見に。
- 褒めポイントを言語化:「今日の歩幅、すごく良かった!」は最高のドーパミン。
ミニ辞典(読み物としての楽しみも)
- レビー小体:αシヌクレインの“足跡”。大きな塊そのものより途中の小塊がトラブルメーカー説。
- フリージング:運動プログラムの切替え失敗。外部キューで回路を“別経路で呼び出す”。
- ウェアリングオフ:薬の切れ目で症状が悪化。**配役の並べ替え(用量・間隔・併用)**で調整。
- DBS:脳内の電気信号を“整える”ペースメーカー。適応の見極めが肝。

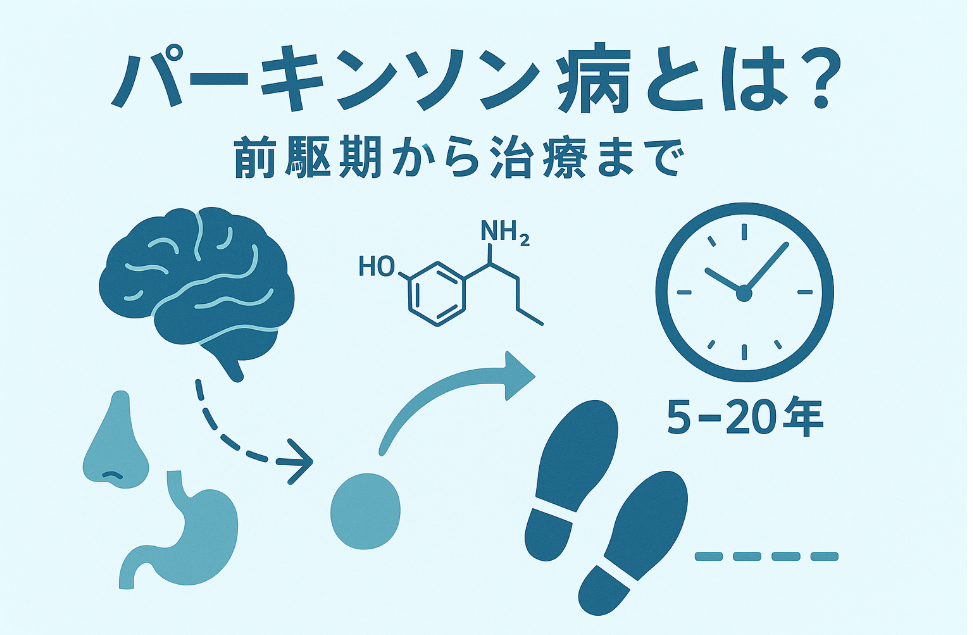
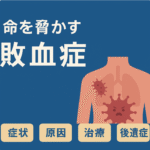
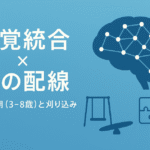
コメント