感染から始まる全身の危機、その実態と回復のための支援を多角的に解説
医療の進歩によって多くの疾患が治療可能となった現代においても、「敗血症(Sepsis)」は依然として世界中で高い死亡率を示す深刻な疾患です。特に高齢者や慢性疾患を抱える人々にとっては、敗血症は単なる感染症の延長ではなく、生命を直接脅かす重大な疾患であり、かつ治療後も長期的な影響を残しやすいという特徴があります。
この記事では、敗血症の定義・原因・症状から、治療の流れ、後遺症、そしてリハビリテーションの重要性に至るまで、多角的な視点で詳しく解説します。現場の臨床家だけでなく、患者・ご家族・地域の支援者にも届くよう、わかりやすく、そして深く掘り下げてお届けします。
■ 敗血症とは何か?
敗血症とは、単なる感染症の悪化ではなく、「感染に対する過剰な免疫反応」によって、全身に炎症が広がり、臓器機能が障害される病態です。感染そのものが問題なのではなく、それに対する体の“暴走した反応”が、むしろ命を危険にさらすのです。
かつては「菌血症(血液中に菌が存在する状態)」と混同されがちでしたが、現在の定義では菌の存在よりも、臓器障害の有無が診断の鍵となっています。国際的には、2016年に改訂された「Sepsis-3」の定義が広く用いられており、「生命を脅かす臓器障害を伴う感染症」とされています。
■ 主な症状:身体の異変に早く気づくことがカギ
敗血症は突然に始まるものではありませんが、その進行は非常に速く、場合によっては数時間で多臓器不全に至ることもあります。以下のような症状が見られた場合には、早急に医療機関を受診する必要があります。
- 高熱または低体温(体温が下がるケースも)
- 意識の混濁、混乱、倦怠感
- 呼吸数の増加、息苦しさ
- 脈が速い、血圧の低下
- 尿の量が極端に減る
- 手足の冷感やチアノーゼ
- 全身に広がる皮疹、出血傾向
これらは「全身の炎症反応症候群(SIRS)」として知られ、敗血症の重要な兆候です。
■ 原因となる感染症と病原体
敗血症の発端となる感染症は、実にさまざまです。代表的なものには以下のような感染症があります。
- 肺炎:特に高齢者や慢性呼吸器疾患を抱える人に多く見られます。
- 尿路感染症:糖尿病や排尿障害を持つ人がかかりやすい。
- 腹膜炎・胆嚢炎:消化器系の感染から波及することがあります。
- 褥瘡感染や皮膚潰瘍:在宅・施設療養中の高齢者に多く見られる。
- 術後感染・カテーテル感染:医療介入に伴う感染リスク。
病原体としては、**グラム陰性桿菌(大腸菌など)やグラム陽性球菌(ブドウ球菌など)**が多く、最近では耐性菌(MRSAやESBL産生菌)の関与も問題となっています。
■ 敗血症性ショックとは?
敗血症がさらに重篤化すると、「敗血症性ショック」という命に直結する状態に至ります。これは、全身の血管が拡張しすぎて血圧が維持できなくなり、臓器に十分な血液・酸素が供給されなくなる状態です。
このとき、心臓・腎臓・肝臓・脳などが急速に障害され、多臓器不全を引き起こします。医療現場では、ICU(集中治療室)への早急な移送と、血圧を維持するための昇圧剤投与、輸液、人工呼吸器管理などが行われます。
■ 治療戦略:「1時間以内」が生死を分ける
近年、「敗血症バンドル」と呼ばれる一連の治療プロトコルが整備され、「最初の1時間以内」に抗生剤を投与することが推奨されています。この初動の遅れが、生存率に大きく影響することがデータでも示されています。
治療の柱は以下のとおりです:
- 広域スペクトル抗生物質の早期投与
→ 原因菌が不明でも、先手を打つ。 - 大量の輸液による循環維持
→ 血圧と臓器灌流を確保する。 - 感染源のコントロール(ソースコントロール)
→ ドレナージ、手術、カテーテル抜去など。 - ICUでの多臓器サポート
→ 呼吸、腎機能、血糖、栄養、鎮痛鎮静管理を含む。
治療はチーム医療が鍵であり、医師・看護師・薬剤師・臨床工学士など多職種の連携が求められます。
■ 廃血症の後遺症と「ポストICU症候群(PICS)」
治療に成功しても、敗血症の後遺症に悩む人は少なくありません。代表的な後遺症は以下の通りです:
- 筋力の低下・歩行障害(ICU-AW)
- 認知機能低下・注意力障害
- うつ・不安・PTSD
- 腎機能障害(慢性腎不全への移行)
- 生活機能(ADL)の低下
これらを総称して「ポストICU症候群(PICS)」と呼び、敗血症の長期的なQOLに影響を与えることが明らかになっています。
■ リハビリテーションの重要性
敗血症からの回復には、急性期治療だけでなく回復期・生活期の支援が不可欠です。リハビリテーション専門職(PT・OT・ST)による早期介入が、ADL(日常生活動作)の回復や在宅復帰に大きく寄与します。
また、筋力や認知機能の回復には「段階的・個別的なリハプログラム」が必要であり、退院後も地域包括ケア、訪問リハ、外来フォローが重要です。
■ 患者家族への支援と社会的意義
敗血症は患者だけでなく、家族にとっても精神的・経済的な負担が大きい疾患です。長期入院、介護負担、再発への不安…。こうした家族への心理的支援、相談支援、介護保険制度との連携も、現代の医療に求められる視点です。
また、敗血症は高齢化社会の日本において、今後ますます医療・介護における重要テーマとなっていくでしょう。予防啓発や感染対策も含め、地域全体で取り組むべき課題でもあります。
■ まとめ:敗血症を「知る」ことは命を守る第一歩
敗血症は、決して特殊な病気ではありません。風邪や尿路感染、皮膚のちょっとした炎症など、「よくある感染」がきっかけで発症することもあるのです。
だからこそ、「体調がいつもと違う」「熱が下がらない」「意識がもうろうとしている」など、何気ない症状を見逃さないことが大切です。
そして、医療者・患者・家族・地域が連携して、早期発見・早期治療・早期リハビリ・継続的支援というサイクルを構築していくことが、これからの敗血症対策には欠かせません。

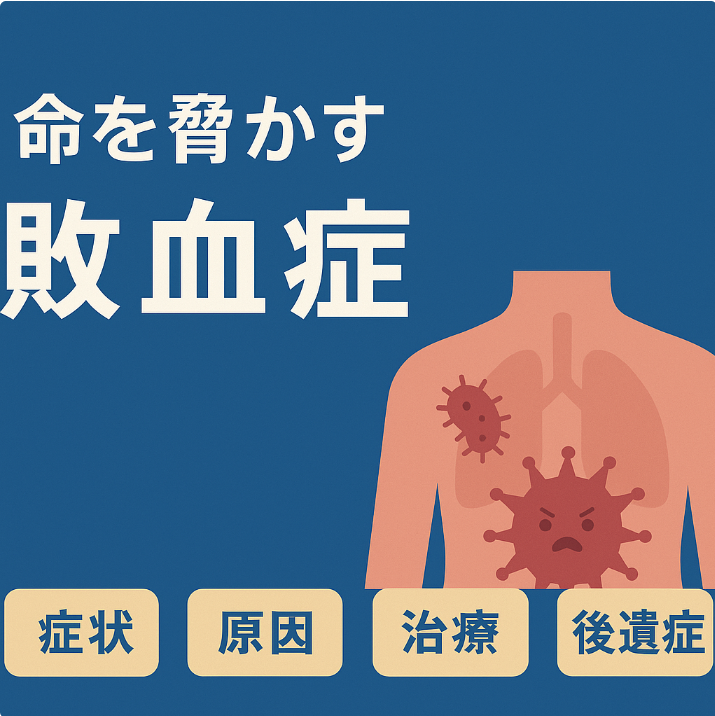

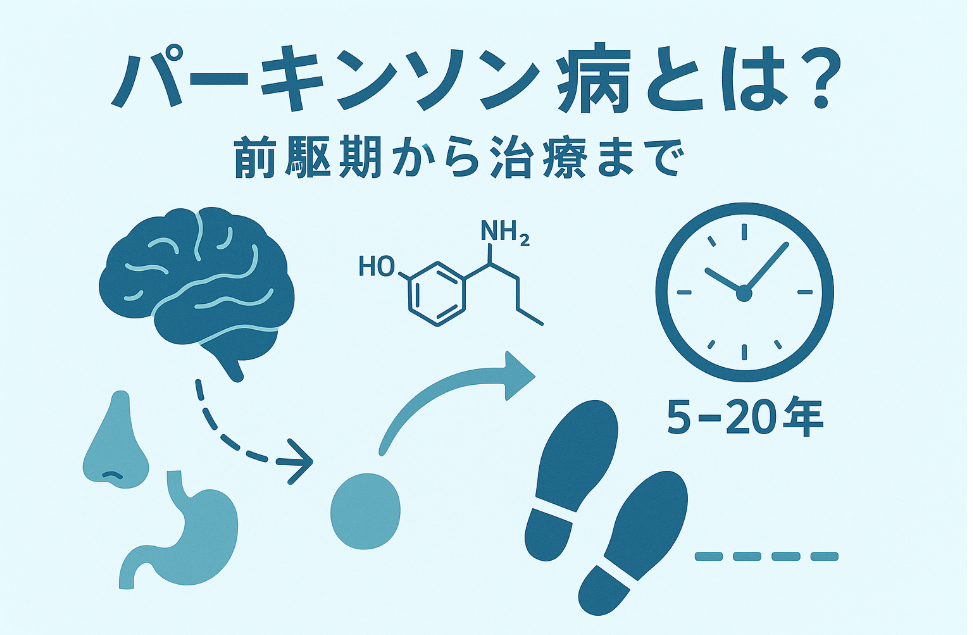
コメント