レントゲン/マンモグラフィ/CT/MRI・fMRI/超音波(エコー)/SPECT・PET/脳波/骨密度/カロリックテスト
レントゲン(一般X線)
なにをしている?
強い光の仲間である「X線」を体に通し、どれくらい通り抜けるかの差で影絵を作ります。かたい骨は白く、空気は黒く写ります。
装置の中で起きていること
電子をぶつけてX線を作り→体を通して→受け皿(センサー)で光や電気に変えて画像にします。
ポイント:設定を変えると「抜けやすさ(コントラスト)」や「ザラつき(ノイズ)」が調整できます。
マンモグラフィ(乳房のレントゲン)
なにをしている?
乳房をやさしく圧迫して薄くし、細かい石灰化や小さなしこりを見つけやすくします。乳房専用のレントゲンです。
装置の中で起きていること
乳房が見やすい“低めのエネルギーのX線”を作り、細かい点まで拾える高精細なセンサーで受け取ります。
ポイント:少し角度を変えて何枚か撮り、薄い層ごとの画像に組み立てる方式(トモシンセシス)もあります。
CT(輪切りのレントゲン)
なにをしている?
体の周りをぐるっと回りながら、いろいろな方向からレントゲンを撮って、コンピュータで「輪切りの写真」に組み立てます。
装置の中で起きていること
たくさんの方向から集めたデータを、計算でサンドイッチの1枚1枚のように再現します。
ポイント:最近は計算を工夫して、少ない線量でもきれいに写せるようになっています。色のつく薬(造影剤)で血管や腫瘍も見やすく。
MRI(強い磁石と電波を使う)
なにをしている?
体の中の「水」の信号を読み取って、柔らかい組織(脳・筋肉・靭帯など)をくっきり映します。放射線は使いません。
装置の中で起きていること
強い磁石で体の水素を整列→電波を当てて少しだけ“揺らす”→元に戻るときの小さな信号を聞き取り、場所ごとに地図にします。
ポイント:撮り方(T1/T2/拡散など)を変えると、炎症・むくみ・急性脳梗塞など、見え方が変わります。
fMRI(脳の“働き”を見るMRI)
なにをしている?
脳がよく働くと、その場所に血が多く流れます。血の中の酸素の状態変化をヒントに、今どこが活動しているかを推定します。
※ 神経の電気を直接見ているのではなく、「血流の変化」という間接的なしるし(BOLD信号)を見ています。
超音波(エコー)
なにをしている?
聞こえないほど高い音(超音波)を体に入れて、跳ね返ってくる音で臓器の形や動きをリアルタイムに映します。ジェルは“空気をなくして音を伝えやすくするため”に塗ります。
装置の中で起きていること
プローブの中の部品が「電気→振動(音)」に変換し、戻ってきた音は「振動→電気」に戻して測ります。
ポイント:音の高さの変化(ドップラー効果)で血の流れの速さや向きも測れます。
SPECT(スペクト)と PET(ペット)
どちらも少量の“光る薬(放射性医薬品)”を使って、体のはたらき(血流・代謝)を地図にする検査です。
SPECT
なにをしている?
薬から出る光(ガンマ線)を直接カメラで拾い、体を回りながら集めたデータを立体に組み立てます。
ポイント:カメラの前に“穴の空いた鉛の板(コリメータ)”を置き、特定方向の光だけを通して、ぼやけを減らします。
PET
なにをしている?
薬から出る“陽電子”が体の中の電子とぶつかって、向かい合う方向に同時に光(ガンマ線)が2本飛びます。その2本を同時に捉えて、どこで起きたかを割り出します。
ポイント:2本の時間差まで使って場所をより正確に絞り込む技(TOF)もあります。腫瘍の代謝の強いところが光って見えます。
脳波(EEG)
なにをしている?
頭の皮ふに小さな電極をつけて、脳が作るとても弱い電気のゆれを“波”として記録します。ミリ秒単位の速い変化に強いのが特徴です。
装置の中で起きていること
脳の表面近くの神経細胞がいっせいに活動すると、弱い電気が頭皮まで伝わります。それを増幅して、時間ごとの波にします。
ポイント:時間の変化に強い一方、「どこの深さか」を細かく特定するのは苦手です。
骨密度(DXA)
なにをしている?
強さの違う2種類のX線を同時に使い、骨とその他(筋肉や脂肪)をうまく“引き算”して、骨のミネラル量を計算します。
装置の中で起きていること
2色のX線の吸収の差から、骨だけの成分を取り出す算数をしています。
ポイント:結果はBMD(骨密度)やTスコアで示され、治療前後の変化も追えます。
カロリックテスト(前庭の温度刺激)
なにをしている?
耳の穴に温かい水や冷たい水(または風)を入れて、バランスのセンサー(半規管)をわざと刺激します。その結果、目が一定方向に動く(眼振)ので、その反応で左右の機能差を調べます。
装置の中で起きていること
温度で耳の中の液体がわずかに流れ、センサーが傾いたと勘違い→目が反射的に動く。カメラでその動きを記録して評価します。
ポイント:「冷たい刺激で反対向き、温かい刺激で同じ向き」に目の速い動きが出る、という基本ルールがあります。
まとめ
- レントゲン/CT:X線で「形」をみる。CTは輪切りで立体的。
- MRI:磁石と電波で「水の信号」を聞いて、柔らかい組織をくっきり。fMRIは血流の変化から“働き”を推定。
- 超音波:音の反射とドップラーで「形+動き+血流」をリアルタイムに。
- SPECT/PET:光る薬で「はたらき(血流・代謝)」の地図を作る。
- 脳波:脳の弱い電気を“今この瞬間”の速さでとらえる。
- 骨密度:2色のX線で骨だけを計算して取り出す。
- カロリック:温度でバランス器官を刺激し、目の動きで左右差をみる。



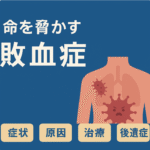
コメント