──AIは“彼”を理解できるのか?
はじめに:言葉の背後にある「意味」をAIはつかめるか?
人間にとって、会話の中の「彼」「それ」などの代名詞が何を指しているのかを理解することは、さほど難しくありません。たとえば、
A「彼女が泣いていたのよ。」
B「彼が怒ったからだろうね。」
この「彼」が誰を指すのか、私たちは文法だけでなく、感情の流れ、社会的背景、登場人物同士の関係性などから総合的に判断しています。
しかしAIにとっては、このような**“当たり前”の理解**が非常に難しいのです。
この課題を浮き彫りにするのが、「ウィノグラード・スキーマ・チャレンジ(Winograd Schema Challenge, WSC)」です。
1. ウィノグラード・スキーマとは?
WSCは、2012年にトロント大学のHector Levesque教授らが提唱した人工知能の常識理解力を測るためのテストです。
チューリングテストのように曖昧な「会話能力」ではなく、「文章の意味を本当に理解しているのか?」という点をピンポイントで問う試験です。
例題(典型的なウィノグラード・スキーマ):
“The trophy doesn’t fit into the suitcase because it is too big.”
→「it」が指すのはどちら?トロフィー?スーツケース?
文法だけでは決定できません。人間は常識的に、「大きいのはトロフィー」と判断します。
AIもこのような推論をできるか?これがチャレンジの本質です。
2. 「選択的制約」──AIが理解に使える言語的ヒント
ウィノグラード・スキーマを解くカギの一つに、「選択的制約(Selectional Restriction)」という概念があります。
これは、ある語(特に動詞)が、意味的に取りうる主語・目的語の範囲を制限することを指します。
例:
- ✅「赤ちゃんがミルクを飲んだ」 → 自然
- ❌「赤ちゃんがハンマーを飲んだ」 → 不自然
このように、「飲む」という動詞には「液体など飲めるもの」を目的語に取るという制約があり、これは常識と結びついています。
ウィノグラード問題でも、この制約が代名詞の解釈に関わる場面があります。
3. 感情や意図を読み取るという難しさ
もう一つのポイントは、「感情」「意図」「人間関係」といった、非言語的な情報の処理です。
例:
「ジョンはポールを殴った。彼は後悔していた。」
“彼”はどちらでしょう?文だけでは決まりません。
- ジョン(殴った側)が後悔している?
- ポール(言動を挑発した側)が後悔している?
この判断には、**心理学的推論(誰がどう感じるか)**や、**社会的価値観(暴力を振るう側の後悔)**などの文脈的・文化的知識が必要です。
4. チューリングテストとの違い
ウィノグラード・スキーマは、伝統的なチューリングテストのような「人間らしく答えるか」ではなく、人間のような推論ができるかを問う、より本質的な知能評価です。
- チューリングテスト:曖昧な会話能力
- WSC:明確な二択で、推論力を判
5. AIは「常識」や「感情」をどう処理しているのか?
ウィノグラード・スキーマ・チャレンジ(WSC)で求められるのは、文法的正しさではなく、常識に基づく推論や感情の理解です。これをAIがどのように獲得していくのかは、近年の人工知能研究の最前線です。
(1) 感情推定モデル:AIが「誰がどう感じたか」を読む
✔ 例:
「彼女が声を荒げた。彼は悲しそうだった。」
ここで「彼」の感情を理解するには、社会的なやり取りに関する知識が必要です。
AIは、EmoNetやGoEmotionsのようなデータセットを使い、文中の登場人物の感情状態を推定するモデルを学習しています。
- 🤖 「声を荒げる」=怒り
- 🤖 「怒られる」=悲しみ/後悔
このような因果的感情推定は、照応解析のヒントになります。
(2) 常識知識ベース:ConceptNetやATOMICの利用
人間が日常的に持つ常識(「氷は冷たい」「怒ると相手は怖がる」など)を、AIが扱えるように構造化したのが**常識知識ベース(commonsense knowledge bases)**です。
代表的なもの:
| 知識ベース | 特徴 |
|---|---|
| 🧠 ConceptNet | 言葉同士の意味関係(例:knife → used for → cutting) |
| 🔁 ATOMIC | 人間の行動と感情・反応の因果関係(例:apologize → person feels relief) |
これらの知識を使えば、AIは「誰が泣いたのか」「なぜ怒ったのか」といった隠れた因果構造を推測できるようになります。
(3) 長文文脈モデル:GPTやBERTの進化
GPT-4などの大規模言語モデル(LLM)は、数千トークン分の文脈を保持し、前後の文の関係を踏まえて代名詞や話者の意図を推定します。
進化のポイント:
- 従来のモデル:直前の文にだけ反応 → 短絡的な推定
- GPT-4以降:文脈を保持しつつ、過去の情報を再利用できる
これにより、「誰が怒っていたか」「なぜ許可されなかったか」といった多段階の文脈推論が可能になりつつあります。
6. それでもAIには難しいこと:非言語的・文化的知識
AIは膨大なコーパスからパターンを学習できますが、人間の体験や社会的直感を完全に模倣することはできません。
たとえば:
- 「母親は子どもが泣いていると心配する」
- 「上司に怒鳴られると委縮する」
- 「謝罪すると和解が進む」
これらは文化や人間関係に深く根ざした知識であり、明示的に記述されたデータにないことも多いため、モデルの判断がずれることもあります。
7. 今後の展望:AIと「意味理解」の未来
ウィノグラード・スキーマ・チャレンジは、単なる代名詞の推定にとどまらず、AIが「意味」をどうとらえるかという根源的な問いを投げかけています。
これからのAI研究では:
- 感情・意図・信念の推論(Theory of Mind)
- 多文化的常識の学習
- 人間とのインタラクションによる意味の学習
などがますます重要になります。
終わりに:ウィノグラード・スキーマが示す「知性」の本質
「彼」が誰かを当てるだけの問題に見えて、その背後には人間の知能がいかに多層的・文脈依存的かという深い構造があります。
AIはますます賢くなっていますが、感情・意図・常識といった非言語的情報を“理解”するには、まだ道のりがあります。
ウィノグラード・スキーマ・チャレンジは、そうしたAIの知性の限界と未来を照らす、シンプルで本質的なチャレンジなのです。


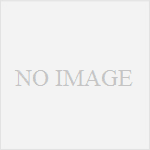
コメント