感覚の特異性・視床の役割・コミュニケーションのコツ・原因と支援の完全ガイド
ASDは“治す/治る”ではなく、特性に合わせて環境・タスク・やり取りを設計し直すことで力を発揮できる発達特性です。
本記事は以下を網羅します:基礎、感覚の特異性(視床=感覚ゲートの視点)、コミュニケーションと社会的相互作用、原因の考え方、すぐ使える支援、就学・就労の合理的配慮、メルトダウン対応、テンプレ集。
目次
- ASDの基礎(強みと困りごと)
- 感覚の特異性:タイプ別の理解と領域別の具体例
- 視床(thalamus)という“感覚ゲート”の見方
- コミュニケーション/社会的相互作用の特性(ことば・非言語・会話運用)
- 背景メカニズム(予測処理・E/Iバランス・実行機能・ダブル・エンパシー)
- 現場で使う10分アセスメント・プロトコル
- 支援の黄金ルール:環境 → タスク → やり取り
- 具体支援:学校・職場・医療での“定番アレンジ”
- メルトダウン/シャットダウンの実践対応
- 1日の“整える”ルーチン(15–20分版)
- ケースで学ぶ:小学生・成人就労の2事例
- すぐ使えるテンプレ集(配布OK)
- よくある質問(FAQ)
- まとめ(チェックリスト付き)
1) ASDの基礎(強みと困りごと)
- 中核の2本柱:
① 社会コミュニケーション/相互作用の特性
② 限定的・反復的な行動・興味・感覚の特性 - スペクトラム:現れ方・強さは人により大きく異なる。
- よくある強み:
深い集中・専門的関心、パターン認識、誠実さ・正確さ、視覚的思考、ルーチン運用の安定性。 - 併存しやすいもの:ADHD、不安/抑うつ、睡眠、てんかん、胃腸症状、協調運動の不器用さ 等。
2) 感覚の特異性:タイプ別の理解と領域別の具体例
4つの現れ方(混在も普通)
- 過敏:小さな刺激も強く感じる
- 低反応:強い刺激でも気づきにくい
- 刺激追求:回転・深圧・強い味などを求める
- 弁別の弱さ:似た刺激の区別が難しく疲れやすい
領域別の典型
- 聴覚:人混み・換気扇音が負荷/呼びかけが雑音に埋もれる
- 視覚:強い照明・ちらつき/掲示多すぎで集中困難
- 触覚:服のタグ・縫い目・食感が苦手/深圧で落ち着く
- 嗅覚・味覚:匂いに敏感/濃い味を好む・選食
- 前庭:揺れが怖い/逆にブランコ・回転を好む
- 固有受容:筆圧弱く姿勢が崩れる/重い物運びで集中UP
- 内受容:空腹・疲労・暑寒の気づきがズレる → 休憩・水分の“時刻化”が有効
Dunnの4象限モデル(感覚閾値×自己調整=4タイプ)
- 低登録/刺激追求/過敏/回避。同じ人でも場面で変わるため“固定タイプ決め”は禁物。
3) 視床(thalamus)という“感覚ゲート”の見方
- 視床は感覚情報を皮質へ渡す中継所兼ゲートで、どの刺激を強め/弱めるかを調整。
- ASDでは視床‐皮質ネットワークの調整差(例:プルビナール核、視床網様核)が示唆され、過敏・低反応・刺激追求の背景になり得ます。
- 実践的含意:
- 「性格」「我慢」の問題ではない → 外付けのゲート(ノイズキャンセラ・間接照明・視線の逃げ場)で補助
- リズム運動・呼吸で同調(ゲイン調整)を助ける
- 予告/見通しで予想外(予測誤差)を減らす
4) コミュニケーション/社会的相互作用の特性
ことば(語用論):比喩・皮肉・遠回しは負荷、返答に時間がかかる、情報量の過不足が出やすい。
非言語:視線・表情の読み取りや、声量・抑揚・距離感の調整が難しい。
会話運用:順番・話題転換・終え方・相手の前提の推測が難しく、誤解が生じやすい。
社会的相互作用:曖昧規範(“空気”“察する”)が負荷。マスキングにより消耗→不安/抑うつ。
5) 背景メカニズム(ざっくり)
- 予測処理(予測符号化)の重みづけ差:曖昧場面で“予想外”を過大に感じやすい。
- E/Iバランスと慣れの遅さ:刺激のゲイン調整が効きづらい。
- 実行機能の負荷:切替え・抑制・作業記憶を同時運用するコスト。
- ダブル・エンパシー問題:困りごとの一部は相互の噛み合わなさでも生じる。
6) 現場で使う「10分アセスメント」
- 困る刺激TOP3/落ち着く刺激TOP3(本人・家族)
- 場面別○×(教室/職場/通勤/家庭/医療)
- 前兆サイン(耳ふさぎ、呼吸浅い、独語増加 等)
- 回復手段(静かな場所、深圧、冷温ペットボトル、水分)
- 環境観察(音・光・匂い・動線・掲示・席)
- 優先順位:①安全 ②疲労低減 ③学習/業務効率
本格評価:Sensory Profile/AASP、語用論評価(CCC-2, CELF, TOPL-2)、適応行動(Vineland)、構造化観察(ADOS-2)など。
7) 支援の黄金ルール:環境 → タスク → やり取り
A. 環境
- 音:静かな席、ノイズキャンセラは“予兆~ピーク時”の短時間使用
- 光:直射→間接/モニタはダークモード/蛍光灯のちらつき回避
- 視覚ノイズ:掲示・机上を“隠す”(半透明ファイル)
- 見通し:今日の流れ+変更点を文字+アイコンで二段階予告
B. タスク
- 短く具体(×「そのうち」→○「8/28(水)17:00まで」)
- 完成見本+優先順位を先に提示/チェックリスト化
- 一度に1質問+選択肢(A/B/C)
C. やり取り(SCIP法)
- Signal(話しかけの合図)
- Choice(選択肢提示)
- Information(補足は短く)
- Pause(待つ)
D. 日本語“高文脈”対策
- あいづちは明示型(「なるほど」「了解です」)
- 冗談・比喩には**〈冗談です〉タグ**
- 敬語はテンプレ運用で負荷を削減
NG⇄OK 言い換え増補
- ×「いい感じに調整して」
→ ○「A社へ(1)期日9/5→9/12、(2)納品順入替を今日17:00までにメール依頼」 - ×「また今度」
→ ○「9/3(火) 15分、Teamsで話しましょう(議題:Aの確認)」 - ×「臨機応変に対応」
→ ○「この3パターンで対応。迷ったらC」
8) 具体支援:学校・職場・医療の“定番アレンジ”
学校:
- 席は壁側/後方、視線の逃げ場を共有/授業予定と変更はシンボル表示
- プリントは余白広め・行間拡大/評価基準は数行で明示
- “抜け道”スペース(静かな席)と自己申告休憩の制度化
職場:
- 事前アジェンダ・議事の型化/チャット中心も可(記録が残る)
- 緊急連絡の明確なトリガー条件(例:Aが起きたらBへ連絡)
- ノイズ・光の調整/1on1の定例・メンター配置/成果の定義を明文化
医療:
- 採血・検査は手順の見える化+回数カウント+選択肢(右/左/姿勢)
- 匂い・音の苦手を事前申告欄に/待合の“逃げ場”確保
9) メルトダウン/シャットダウンの実践対応
予兆:呼吸浅い、眉間のしわ、耳/頭を押さえる、独語増加、視線が泳ぐ
即時対応:①音光を下げる ②短い指示で移動 ③水分 ④深圧/体幹圧
回復:5–15分の無刺激→再開時は短い選択肢
NG:説教・詰問・「我慢して」・長拘束
10) 1日の“整える”ルーチン(15–20分)
- 朝:壁押し1分+呼吸1分→“今日つらい刺激”をカードで共有
- 昼:ノイズ/光オフのミニ退避5分+イススクワット10回×2
- 夕:ぬるめ入浴or足浴10分→就寝前に翌日の見通しを確認
11) ケースで学ぶ:2事例
事例A:小学生(音過敏+語用論の負荷)
- 困り:チャイムや清掃音で耳ふさぎ→授業に戻れない。雑談の冗談を字義通りに受け取りトラブル。
- 介入:
- 突発音の事前予告+“避難席”の指定
- ノイズキャンセラは予兆~ピークだけ使用(常時は逆効果)
- ソーシャルストーリーで「冗談=本気でない」の合図を練習
- SCIPで先生が声掛け → 子どもが選択肢で返答
- 成果指標:週あたり退避回数、授業復帰までの分(ベースライン→介入後の変化)
事例B:成人就労(視覚ノイズ+会議の高文脈)
- 困り:開放オフィスで集中不可。会議の「空気を読んで」指示で混乱。
- 介入:
- 席を壁側へ/視覚ノイズを隠す(ファイル/パーテーション)
- 会議はアジェンダ事前配布、決定基準を明文化
- チャットで要点確認(記録)+1on1定例
- 成果指標:作業完了率、修正指示の回数、会議後のToDo明確度(自己評価1–5)
12) すぐ使えるテンプレ集(配布OK)
12-1. 5分で作る「前兆→避難→回復」カード(A6)
- 前兆:____
- 避難場所:____
- 同行サイン:「今は静かな場所に移動しよう」
- 回復手段:水分/深圧クッション/目を閉じて呼吸
- 再開合図:「もう大丈夫? AとBどちらから始める?」
12-2. 連絡帳・社内チャットで使う“SCIP型”定型文
- Signal:「今いいタイミングですか?」
- Choice:「A案/B案、どちらが良いですか?」
- Information:「締切は8/28(水)17:00です」
- Pause:「一度ここで待ちます。必要なら追記します」
12-3. 教師・上司向け「言い換えリスト」抜粋
- ×「柔軟に」→ ○「この3手順のうち、迷ったら3を選ぶ」
- ×「また後で」→ ○「9/3(火)15:00、15分だけ話す」
- ×「察して」→ ○「Aが起きたらBを実行」
12-4. 個別支援の目標テンプレ(SMART)
- 目標:「授業中の退避を週5回→週2回へ(4週間)」
- 測定:教室記録表
- 達成条件:2週連続で週2回以下
- 介入:事前予告・避難席・ミニ退避5分
- 見直し:毎週金曜に担任と確認
13) よくある質問(FAQ)
Q1. ASDは“慣れ”で治る?
A. いいえ。特性は生涯の“処理のくせ”。慣れさせる前に環境を整えるのが先。段階づけと予測可能性が鍵。
Q2. 薬でコミュニケーションは改善する?
A. 中核症状に直接効く薬は限定的。ADHD、不安/抑うつ、睡眠、易刺激性など併存症状に対して適応を検討し、副作用と効果をモニター。
Q3. 親の育て方が原因?
A. いいえ。遺伝的素因×環境要因×脳回路の発達差という多因子モデル。育て方が原因という考えは誤り。
Q4. 同じASDなのに場面で違って見えるのはなぜ?
A. 感覚負荷・予測可能性・社会的要求が場面ごとに違うため。Dunnの4象限は場面で入れ替わります。
14) まとめ(ミニ・チェックリスト付き)
総括
- ASDは神経発達の特性。強みと困りごとがセットで現れる。
- 感覚の特異性は回路の特性(視床ゲート含む)。外付けの補助と予測可能性で整える。
- **コミュニケーションの難しさは“相互のミスマッチ”**でも起きる。
- 環境→タスク→やり取りの順で設計すると、ムダな負荷を削り力が引き出せる。
今日から使う5つの行動
- 今日の流れと変更点を文字+アイコンで提示
- 席・照明・音の調整/視覚ノイズは“隠す”
- 指示は具体・短文・期限つき/完成見本を先に
- 一度に1質問+選択肢
- 前兆→避難→回復カードを共有

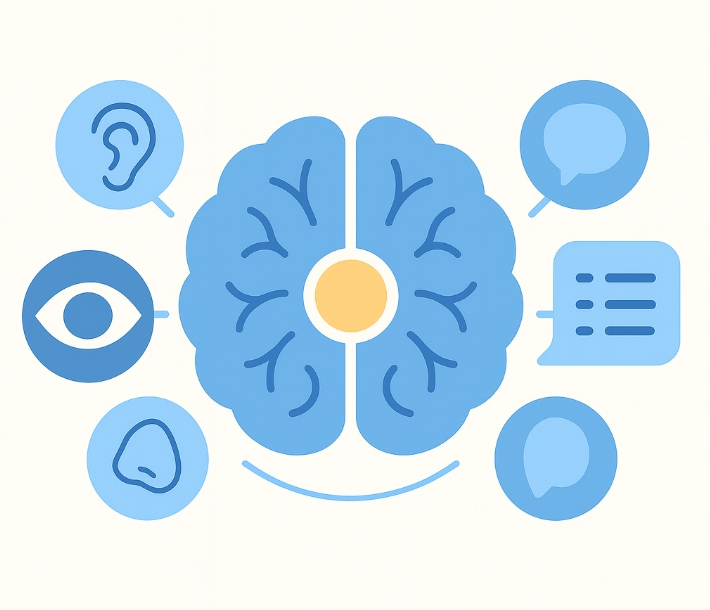


コメント