はじめに
ウェルニッケ失語は聴理解の低下を中心とする流暢型の失語で、しばしば**ジャーゴン様(意味の通らない流暢発話)**を伴います。背景には、音韻解析(音の並びの処理)と語彙‐意味マッピングのネットワーク障害があり、耳から入った音を意味へ橋渡しする経路がうまく働かなくなります。本記事では、症状像、神経メカニズム、評価とリハ、家族対応のコツまでをまとめました。
1. ウェルニッケ失語とは
- コア症状
- 自発話:流暢・多弁だが内容が空疎、錯語や新作語が混在、ジャーゴンになることも。
- 聴理解の低下:単語レベルから取りこぼし、文になると一層困難。
- 復唱障害:聞き取って正確に繰り返すことが難しい。
- 呼称障害:錯語や回りくどい説明に置換。
- 読字・書字の障害:音韻・意味の両側面でつまずく。
- 病識低下:自分の言語障害に気づきにくい。
- 構音・抑揚は比較的保たれ、**「よく喋れているように見える」**のが特徴。
- 病巣(ざっくり)
左上側頭回後部(いわゆるウェルニッケ野;BA22)~縁上回(BA40)・角回(BA39)など側頭‐頭頂境界。 - 経過
回復に伴い伝導失語→健忘失語へ遷移することがよくあります。予後は病巣の広さ・年齢・早期介入などで変わります。
2. ジャーゴン失語とは
- 定義:聞き手にとって了解不能な流暢発話が前景化する失語。ウェルニッケ失語の重症相で典型。
- 特徴:
- 音韻性錯語(/いぬ→いむ/)、語性錯語(犬→猫)、新作語(存在しない語)の多発。
- 理解・復唱の障害、病識の乏しさ。
- ジャーゴン書字(書字でも意味不明)を伴いやすい。
- サブタイプ:音韻ジャーゴン/新作語ジャーゴン/語性(意味)ジャーゴン(混在も多い)。
- 鑑別:
- ブローカ失語(非流暢・理解比較的保たれる)
- 伝導失語(理解比較的良い・復唱のみ強く障害)
- 超皮質性感覚失語(理解低下だが復唱は保たれる)
- 発話例(イメージ) 「きのうテベリがグララして、わたしまどおあけたの」
「きのうはパラシコがドマリで、シャンタをもらった」
3. 「音→意味」の変換はどこで壊れる?(やさしい神経メカニズム)
正常パイプライン(超要約)
- 音響処理(一次聴覚野~上側頭回)
- 音韻解析(左後部上側頭回/上側頭溝・縁上回):
音の連なりを音素・音節に切り、語の切れ目を推定 - 語彙アクセス(中~後部側頭葉):
音列から**語の候補(コホート)**を立ち上げ、最適解を選択 - 語彙‐意味マッピング(角回・前側頭葉など):
選ばれた語を意味ネットワークへリンク - 自己モニタリング(自分の発話を聴いて照合・修正)
中核はpSTG/STS(音韻)→MTG/ITG/AG/ATL(意味)へ至る腹側ストリーム。
壊れ方と症状対応
- A. 音韻解析の破綻(pSTG/STS・SMG)
最小対弁別が不良、語境界の誤り、非語復唱の弱さ、音韻性錯語↑ - B. 語彙アクセスの不安定(MTGなど)
候補選択に迷い、語性錯語や低頻度語での破綻 - C. 語彙‐意味マッピングの断線(MTG/ITG↔AG/ATL)
「聞こえるのに入らない」、新作語↑、自己モニタリング低下
※多くはA+B+Cが重なり、ウェルニッケ~ジャーゴン像をつくります。白質路(IFOF/ILF/鈎状束など)も“配線”として重要です。
4. ベッドサイド評価のポイント
- 音韻:/か/と/が/、/さ/と/ざ/など最小対弁別(聴覚・視覚)
- 復唱:単音節→多音節→非語(既知意味をもたない語)
- 語彙アクセス:語/非語の語彙判断、呼称(ヒント反応を見る)
- 意味:同義判定、カテゴリー/連想(「犬–骨–猫–車」など)
- モニタリング:自発話の即時再聴→誤り検出・修正
目安:非語復唱が特に弱い→音韻バッファの弱さ。ヒントで急改善→アクセス障害優位。意味連想×→マッピング側の問題。
5. リハビリテーションの実践
機能(インペアメント)ベース
- 聴理解の段階づけ:単語→短文→複文、絵‐語マッチング、キーワード法
- 音韻処理:PCA(Phonological Components Analysis)、音節分解、リズム同期復唱、口形の視覚化
- 語彙‐意味:SFA(Semantic Feature Analysis)、カテゴリー化、連想、意味マップ
- 読み書き再結合:音読→意味確認→書き取りの循環(かな/漢字で難易度調整)
- 自己モニタリング:ゆっくり発話→自己聴取→差分言語化→修正
参加(コミュニケーション)ベース
- PACE法/会話志向訓練:言語+ジェスチャー+描画+指差し+写真を統合
- SCA(Supported Conversation for Adults with Aphasia):情報の見える化で理解を補助
- AAC:絵カード、ボード、タブレット
- 集中的訓練(CIAT など):非流暢型でエビデンスが強いが、語彙・音韻課題を厚めに調整して実施
先進的補助(選択)
- tDCS/rTMSの併用は研究段階。薬物は効果が限定的で症例選択が重要。
6. 家族・周囲への対応ポイント
- 短い文・ゆっくり・一度に一つの指示
- キーワードを紙に書く/絵や実物を指す(読字が弱ければ視覚支援を厚く)
- Yes/No 質問で理解確認、うなずき・指差しも活用
- 伝わらなくても別表現で言い直す、責めない
- 疲労で悪化しやすいので短時間×複数回
7. まとめ
- ウェルニッケ失語の三本柱は流暢発話+理解低下+復唱障害。重症相でジャーゴンが目立つ。
- 背景は音韻解析→語彙アクセス→語彙‐意味マッピングのどこか(複数)の破綻。
- 評価は音韻・復唱・語彙・意味・モニタリングの5点を見る。
- リハは音韻・意味の底上げと多感覚の橋渡し、自己モニタリングの手続き化、環境調整が鍵。

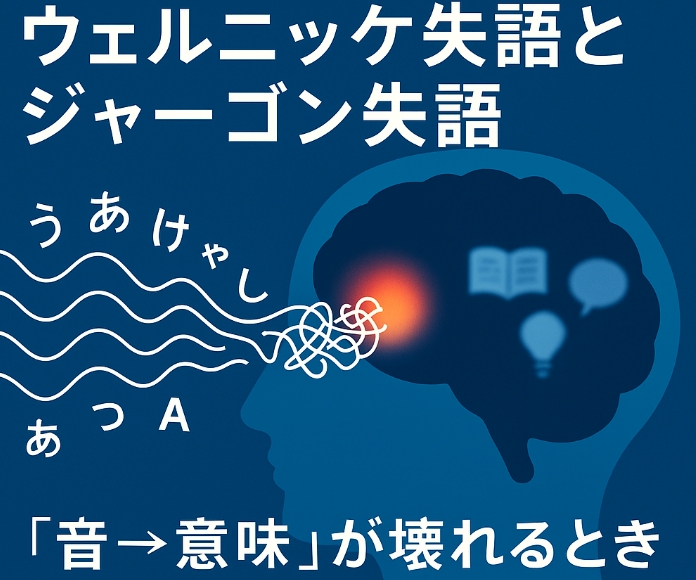
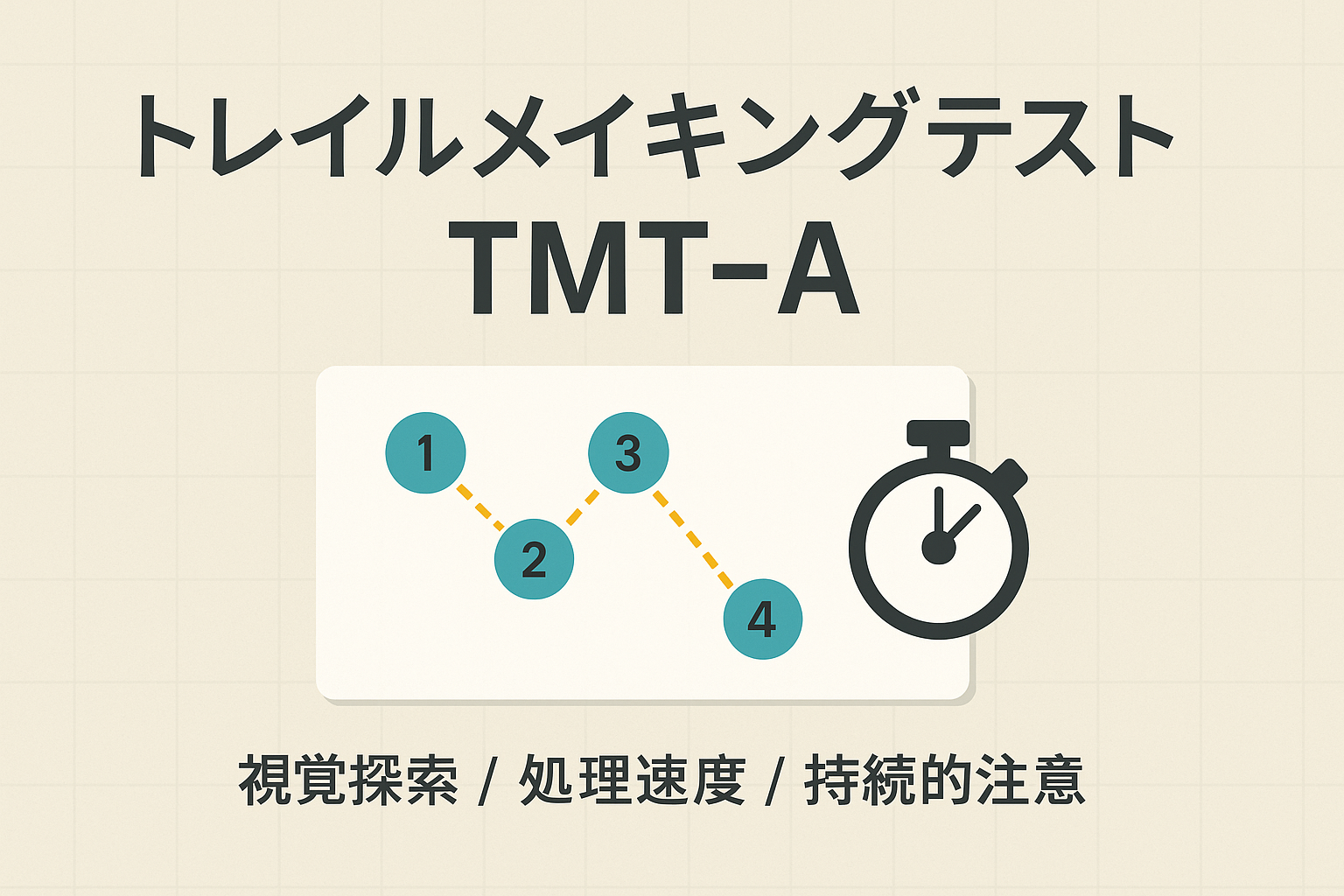

コメント