**TMT(Trail Making Test:トレイルメイキングテスト)**は、紙筆で短時間に実施できる“実行機能スクリーニング”の定番検査です。この記事では、臨床現場でそのまま役立つように、検査の構造、そこから読み解ける認知機能・注意機能、**日本語版(仮名使用)**のポイント、**歴史(誰が作った?)**までを一つにまとめます。内容は本記事のやり取り(本チャット)で説明した範囲に限定しています。
1. TMTは何を測る検査?
- Part A(TMT-A):1→2→3…と数字だけを線で素早く正確につなぐ。
→ 視覚探索・処理速度・持続的注意を中心に評価。 - Part B(TMT-B):1→A→2→B→3→C…のように数字と文字を交互につなぐ。
→ セットシフティング(課題の切替)・注意配分・ワーキングメモリ・反応抑制など実行系注意を強く評価。
短時間・紙筆・ベッドサイド可という利点があり、実行機能のスクリーニングとして広く使われます。
2. 検査の構造(AとBの違い)
TMT-A(Part A)
- 配置:1〜25の数字入り○が紙面にランダム配置。
- 課題:1→2→3…の連番を線で結ぶ。
- 採点:完了までの時間(秒)が主指標。誤りはその場で指摘し戻って修正、所要時間に含める。
TMT-B(Part B)
- 配置:数字(1〜13)と文字(A〜L など)がランダム配置(合計25)。
- 課題:数字と文字を交互に 1→A→2→B→3→C… と結ぶ。
- 採点:完了時間(秒)が主指標。交互ルール違反等は即時訂正、時間に含める。
実施のコツ
- 練習問題(特にB)でルール理解を確認。
- 計時は最初の線を引き始めた瞬間〜最後の正答到達まで。
- 誤りは即時指摘して戻す(“修正コスト”も含めて能力を測る設計)。
- 記録:時間(秒)・誤り数・自己修正の有無・探索の癖・ペン離れ等の質的所見。
3. 構造から見える「機能マップ」
Aが主に反映する機能
- 視覚探索:次の数字をすばやく見つける。
- 連続的系列化:数直線の順序を頭の中で保持。
- 処理速度/精神運動速度:視覚→運動の総合スピード。
- 選択的注意・持続的注意:必要な刺激選択と一定時間の維持。
→ 単一ルール課題として、基礎的な速度と効率をまとめて負荷。
Bが追加で強く負荷する機能
- セットシフティング:数字系列と文字系列を交互に切替。
- ワーキングメモリの更新:二つのルールを保持・更新し続ける。
- 反応抑制:片方に“流される”のを止める(保続を抑える)。
- 分配/交替性注意:注意資源を行き来させる。
→ 二重ルールの同時保持+頻回の切替を要求するため、**実行機能(前頭葉系)**の負荷が大。
注意ネットワークへの当てはめ(簡略)
- Orienting(定位):A・Bとも、次の目標へ注意を素早く移す。
- Alerting(覚醒・警戒):A・Bとも、単調課題で覚醒水準を保つ。
- Executive(実行制御):B>A(競合ルールの監視・切替・抑制)。
4. 指標と読み方(臨床ショートカット)
- 主指標:TMT-A(秒)、TMT-B(秒)。
- 派生指標:
- B−A(差)=純粋な切替コストの目安。
- B/A(比)=個人の基礎速度(A)を補正した相対的切替負荷。
- 質的所見(エラー様式と対応機能の例):
- 系列化エラー(順番飛ばし)=系列保持/ワーキングメモリ。
- ルール違反(交互を忘れる)=セット維持・更新の脆弱/抑制低下。
- 保続(数字ばかり続ける等)=柔軟性低下・抑制低下。
- 近接錯誤(近い円に吸い寄せられる)=選択的注意の脆弱。
- 空間偏倚(片側の見落とし)=視空間注意の偏り。
- 過度のペン離れ・躊躇=探索計画/実行制御の負荷に脆弱。
Aが遅い=処理速度・探索効率の低下(運動・視覚要因も吟味)。
Bだけ特に遅い=切替・更新・抑制(実行機能)の負荷で破綻しやすい。
5. 日本語版(仮名使用)のポイント
日本の運用では、TMT-Bでローマ字(A–L)の代わりに仮名(多くはひらがな)を使う版が一般的です。典型例は1–あ–2–い–3–う…–13(仮名は「あ〜し」で計12字)、数字13個+仮名12個=計25個を交互に結ぶ形式。
標準化された日本語版(TMT-J)があり、「数字と五十音を交互に一筆書きで結ぶ」手順が明記されています。レイアウトは縦版/横版などの違いはあっても、**“数字と仮名の交互結合”**という核は共通です。
英字に不慣れな方では、言語依存性を下げた**Color Trails Test(色の交互結合)**と使い分ける判断も有効です。
6. 疾患・症候との関係(典型的パターンの見立て)
- 脳血管障害:右半球損傷で探索の空間偏倚、前頭葉/皮質下損傷でBの著明低下。
- 外傷性脳損傷(TBI):Bの延長とエラー増加(注意/実行機能)。
- 認知症:アルツハイマー病では進行とともにA・Bとも延長、前頭側頭型ではBの障害が目立つことが多い。
- パーキンソン病:セットシフト困難→B延長。
- ADHD・精神疾患:注意の持続と切替の困難が成績に反映。
- 運転適性:特にBは、切替・注意配分に関わる処理と関連し、スクリーニングでの利用がある。
※最終判断は年齢・教育歴などの背景と他検査(Stroop/Symbol Digit/Digit Span 等)やADL情報を併せた総合評価で。
7. 交絡要因と限界(“引き算”ポイント)
- 年齢・教育歴の影響が大きい(年齢階級別の規準で解釈)。
- 視力・運動機能・利き手・振戦、失語/識字、意欲・情動の影響。
- 学習効果:短期間の再検で成績が上がりやすい(特にA)。
- 単独では診断できないため、補完検査や臨床観察と統合する。
8. 所見テンプレート(そのまま流用可)
TMT-A:45秒、誤り0。
TMT-B:135秒、誤り2(いずれも自己修正あり)。
B−A=90秒、B/A=3.0。
Aは年齢相応。Bでは交互ルール下で切替に著明な遅延。探索は左上象限で見落とし傾向なし。二重基準下での実行制御に弱さが示唆される。
9. 歴史:誰が作り、どう広まったのか
- 起源(1938年):John E. Partington(一部文献でR. G. Leiterも併記)が“Distributed Attention”の名で原型(Partington’s Pathways Test)を考案。
- 1944年:米陸軍 Army Individual Test Battery(AITB)でTrail Making Testとして採用(A・Bの2部構成)。
- 1950年代:Ralph M. Reitanが脳損傷の指標としての妥当性を系統的に示し、Halstead–Reitan神経心理学バッテリーに組み込み臨床標準へ。
- その後:**Color Trails Test(CTT)**の開発、デジタル版の普及、年齢・教育で層化した規準値の整備など、運用と解釈が洗練。
通説的整理:作ったのは Partington(+Leiter)、臨床に根づかせたのが Reitan。
10. クイックチートシート(現場用まとめ)
- まずAで基礎速度と探索を確認 → 次にBで切替評価。
- 記録は時間+誤り+質的所見(躊躇・保続・空間偏倚・ペン離れ)。
- B−A/B/Aで切替コストを把握(Aで基礎速度をコントロール)。
- 日本語版では数字×仮名の交互(例:1–あ–2–い…)を使用。
- 最終判断は規準表+補完検査+ADL情報で総合評価。
まとめ
TMT-Aは**「単一ルールの連続探索×速度」、TMT-Bはそこに「二重ルールの保持・切替・抑制」**が乗る設計です。構造自体が、**選択的/持続的注意+処理速度(A)**と、実行系注意=切替・更新・抑制(B)を分けて測る“仕掛け”になっています。日本語環境では仮名を用いるBが一般的で、言語依存性への配慮や他検査との併用で、実際の生活場面に即した解釈が可能になります。

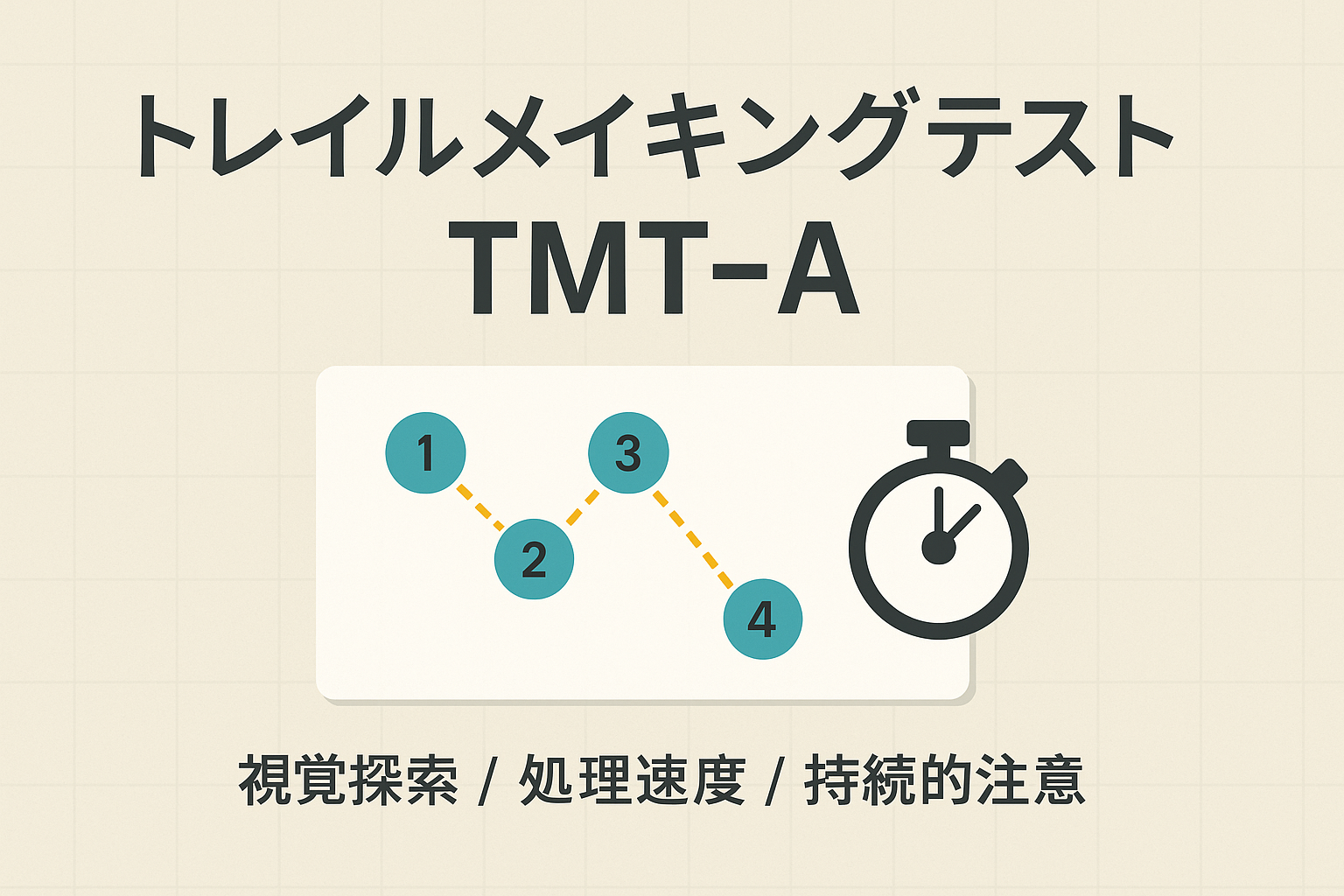
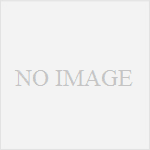

コメント